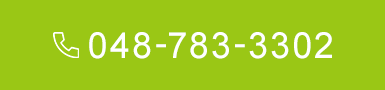第4回です。今回は適応障害と診断された場合、どのような治療をしていくのか、について書いていこうと思います。適応障害は、以前書いたように、不安、落ち込み、不眠、などの症状がみられるのでしたね。結局は、適応障害とうつ病は似通っている部分もあるので、落ち込みに対しては抗うつ薬、不眠に対しては睡眠薬といった具合に対症療法(症状をとりあえずとる治療)になることが多いです。よくあるパターンをあげてみました。
仕事が原因の場合
仕事が原因と言っても、いろいろあります。上司のパワハラや同僚とうまくいっていない、といった人間関係のこともあれば、職場の人間関係はいいのに単に忙しすぎて、家に帰るのが24時頃になるといったこともあります。もちろん、仕事が原因と患者様も主治医も思い込んでいるだけで、実は全然違うところに原因があることもあります。稀ですが、以前書いたように甲状腺の病気だった、ということもあります。ここでは、便宜的に仕事が原因と表現しましたが、100%仕事だけが原因で適応障害とは言い切れないことをご了承ください。上司のパワハラ(といっても本当にパワハラレベルなのか?については私でなくて、会社の調査委員会や裁判所が決めることなのですが)が原因の場合、私なら「上司の上司に相談しましょう」と伝えています。会社によって、本当に対応は様々です。「すぐに動いてくれてパワハラ上司に注意が行き、パワハラがやんだケース」「注意はされたが、パワハラが変わらないケース」「上司の上司が全く動いてくれないケース」などです。ただ、会社の大きさにもかなり影響され、例えば、従業員数人だけの会社で社長のパワハラがひどい場合は、こちらとしても手も足も出ません。正直に社長に嫌な思いをしている旨を伝え、それでも改善が見られないときは転職するしかないように思えます。最近は、だいぶ世間がパワハラや長時間労働に敏感になっているので、大きな会社ほど、そこが徹底されているように感じています。診察をしていると、中小企業を中心として明らかなブラック企業を疑わせる会社も見受けられ、なかなか対応が難しいこともあります。長時間労働の場合は、やはり上司に正直に辛いことを伝えるべきでしょう。上司の反応はこれまた様々。聞いてくれる人、無視する人、逆に説教する人もいます。あまりに落ち込み、不安が強くなり、出社できないレベルと判断される場合は、休職の診断書を書くこともあります。
休職中の過ごし方や治療
休職するほど調子が悪い場合、落ち込みが強く、抗うつ薬が必要になるケースが多いです。まずは、ゆっくりと休息をとることが必要です。パワハラ上司や長時間労働から解放されて、多くの方が多少は改善します。しかし、それだけで完全に病状がよくなり、復職までこぎつけられる人は稀です。医師により、やり方は様々でしょうが、私の場合は、休職して1か月すぎても落ち込みや意欲低下がよくならない場合は、抗うつ薬を勧めることが多いです。当然、会社側も休職を認める際、「休んでもいいから早く治療して良くなって復職してね」という暗黙の了解があります。中には薬に抵抗が強い患者様には、当院ではやっていませんが、他院のカウンセリングを勧めることもあります。ただ、「調子が悪い。医師が抗うつ薬が必要と判断している。でも、薬は飲みたくない。カウンセリング通うのも嫌だ。でも、具合が悪いから休みは延長してほしい。」といった状態が長続きしてしまうと、膠着状態になってしまい、治療がうまくいきません。休職中に、最初のうつ状態がひどすぎる状態の時を除き、患者様にも何らかのアクションが必要になってきます。
今回は、適応障害と診断された以降の対応について書きました。休職中の過ごし方や治療についてはまた別の機会に書いてみようと思います。